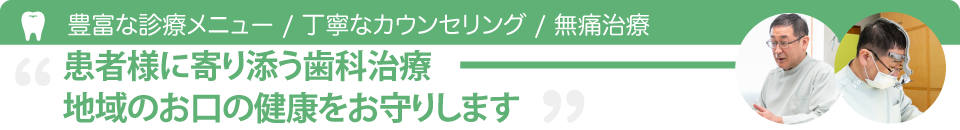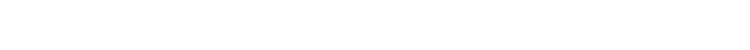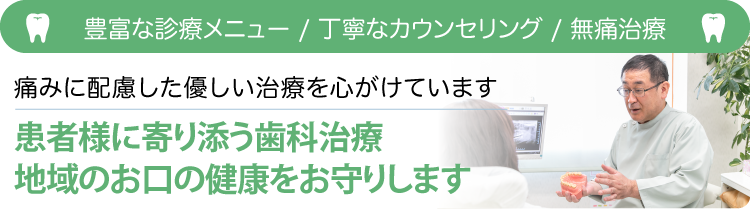こんにちは。鳥取市東町にある歯医者「山根歯科医院」です。

下の前歯が、上の前歯よりも前に出ている状態を、一般的に受け口といいます。子どもの受け口を放置すると、見た目に影響を及ぼすだけでなく発音に支障をきたすこともあります。そのため、治療を検討される保護者の方もいるでしょう。
今回は、子どもが受け口になる理由や受け口を放置するリスク、治療法、予防法について詳しく解説します。
目次
受け口とは

受け口とは、下顎や下の前歯が上顎や上の前歯より前に突き出ている状態を指します。専門的には反対咬合や下顎前突と呼ばれる、噛み合わせの異常のひとつです。
この状態では、前歯で食べ物をうまく噛み切れなかったり、発音が不明瞭になったりすることがあります。見た目のコンプレックスにつながることも多いです。そのため、矯正治療を受けることが推奨されます。
子どもの場合は、顎の成長を利用して治療を行えるケースも多いため、早めの診断と対応が望まれます。
子どもが受け口になるのはどうして?

子どもが受け口になる原因はさまざまで、いくつかの要因が関係しています。
遺伝
まず大きな原因のひとつは遺伝です。親のどちらか、または両方が受け口だった場合、あごの骨の形や大きさが遺伝して、子どもにも同じような噛み合わせの特徴が現れることがあります。
口周りの癖や習慣
日常生活のなかで無意識のうちに行なっている癖や習慣も大きく影響します。例えば、舌で前歯を押す癖、口呼吸、うつぶせ寝、指しゃぶり、おしゃぶりの使用などです。これらの癖や習慣が、顎の成長に偏りを生じさせ、受け口になることがあるのです。
下顎の過成長
上顎に比べて下顎が過度に成長することで受け口になることもあります。下顎が過度に成長する原因のひとつに舌の位置があります。舌先は上の前歯の裏側に触れているのが正しい状態ですが、舌の位置が下がると下顎の成長が促されて受け口になる可能性があるのです。
子どもの受け口を放置するとどんなリスクがある?

子どもの受け口を放置すると以下のようなリスクが生じる可能性があります。
噛み合わせが悪化する
受け口は、歯の噛み合わせが逆になっている状態です。放置すると、成長とともに悪化することがあります。特に下顎の成長が進む思春期以降では、あごのバランスがさらに崩れ、歯並び全体に影響を及ぼすことがあります。
発音しにくくなる
受け口だと、さ行やた行など特定の音が正しく発音しにくくなることがあります。これが原因で会話に支障が出たり、コミュニケーションに自信をなくしたりするお子さんもいます。
見た目がコンプレックスになる
下顎が突き出た顔立ちになるため、外見がコンプレックスになるお子さんもいます。特に思春期以降の自己意識が高まる時期では、心理的なストレスや自信の喪失を招くこともあるでしょう。
顎関節や筋肉に負担がかかる
噛み合わせが正しくないと、食べ物を噛むときに余計な力がかかり、顎の関節や筋肉に負担がかかる可能性もあります。これによって、顎関節症や頭痛、肩こりなどにつながる場合もあります。
治療が難しくなる
成長が進むにつれて、受け口の矯正には時間や費用が多くかかる傾向にあります。特に大人になってからの治療では、外科手術が必要になるケースもあり、負担が大きくなります。
子どもの受け口はどうやって治療する?

子どもの受け口の治療は、成長段階に合わせて行われます。ここでは、主な治療法をご紹介します。
マウスピース型装置を使用した治療
子どもの受け口を改善するために、マウスピース型の装置を使用して治療を行うことがあります。取り外し可能なマウスピース型の装置を、寝ている間や日中の数時間装着することで、舌や口の周りの筋肉のバランスを整え、自然な噛み合わせへと導いていきます。
痛みはほとんどないため、小さなお子さんでも継続しやすいのが特長です。ムーシールドやプレオルソが代表的な装置の種類です。
上顎を広げる装置を使用した治療
上顎の成長が不十分であることが原因で受け口になっている場合には、上顎を広げる専用の矯正装置を使った治療を行ないます。子どもの場合は、顎の成長を利用した治療が可能です。
具体的には、床矯正という治療法があります。上顎に装置を装着し、埋め込まれたネジを回すことで上顎の幅を広げます。床矯正で使用する装置も取り外しが可能なため、食事や歯磨きに支障がなく、痛みも少ないです。
口の外に装着する装置を使用した治療
受け口の治療には、口の外側に装着する矯正装置を使用する方法もあります。チンキャップが代表的な装置です。チンキャップと呼ばれる装置を装着することで、下顎の成長を抑制します。
この装置は下顎が過度に成長している場合に用いられることが多く、治療効果が高いとされている装置です。
何歳から受け口の矯正を受けるとよい?

受け口の治療は、できるだけ早い段階で始めるのが望ましいとされています。特に、乳歯が生えそろう3〜4歳ごろから歯科医師の診察を受けることで、早期発見・対応が可能になります。
乳歯の時期の受け口は、永久歯が生えるときに自然に治るケースもあります。実際には、乳歯から永久歯に生えかわる6〜10歳ごろに治療を開始することが多いです。
成長段階にある子どもは、顎の骨の発達をコントロールしやすいため、適切な時期に治療を開始すれば、抜歯を回避できる可能性もあります。
ただし、治療開始のタイミングには個人差があり、成長のスピードや受け口の程度によっても異なります。そのため、歯科医師に相談のうえ、お子さんの成長に合った判断をすることが大切です。
子どもが受け口になるのを予防するためには

子どもが受け口になるのを予防するためには、以下のことを心がけましょう。
歯並びに影響を及ぼす癖や習慣を改善する
受け口を引き起こす原因のひとつに、日常的な癖や習慣があります。指しゃぶりや舌を前に押し出す癖、口呼吸などの習慣がある場合は、あごの発達や歯並びに影響を与えることがあるため早めの改善が求められます。
日常生活のなかで意識的にやめるように心がける努力が必要です。保護者の方のサポートも不可欠でしょう。
良く噛んで食べる
あごの骨をしっかり発達させるためには、噛むことが非常に重要です。やわらかいものばかりを食べていると、あごの筋肉が十分に使われず、あごの成長が妨げられることがあります。繊維質の多い野菜や、少しかたい食材を取り入れ、よく噛んで食べるようにしましょう。
正しい姿勢を心がける
普段の姿勢も、あごの成長や歯並びに関係します。例えば、猫背になると、下顎が前に突き出やすくなります。また、うつ伏せ寝が習慣になっていると、あごの位置にズレが生じて不正咬合の原因となる場合があります。
そのため、正しい姿勢を心がけることが大切なのです。食事や勉強のときは正しい姿勢を心がけ、寝るときは仰向けの姿勢を習慣づけましょう。
定期的に歯科医院でチェックを受ける
定期的に歯科医院でチェックを受けることも大切です。受け口の初期兆候を見逃さないためにも、3歳ごろから定期的に歯科検診を受けることが推奨されます。
万が一、歯並び・噛み合わせに異常が起こっていても、定期的に歯科医師のチェックを受けていれば、必要なタイミングで予防的な処置を受けられます。早期対応ができれば、本格的な矯正治療を避けられる場合もあるでしょう。
まとめ

子どもが受け口になるのには、親からの遺伝など先天的な原因と、日常的な口周りの悪い癖などの後天的な原因があります。
子どもの受け口は、永久歯が生え揃うなかで自然と改善する場合もありますが、放置すると噛み合わせが悪化したり、複雑な治療が必要になったりするケースもあります。早めに対処することで、将来的に矯正治療が必要になった場合でも負担を軽減できるでしょう。
子どもの受け口の治療は、永久歯が生え揃う10歳までに行うことが理想です。
ただし、顎の成長スピードや歯並びは一人ひとり異なるため、歯科医師に相談のうえ、お子さんに合ったタイミングで治療を開始することが大切です。お子さんの受け口が気になる場合は、歯科医院で相談してみましょう。
小児矯正を検討されている方は、鳥取市東町にある歯医者「山根歯科医院」にお気軽にご相談ください。
当院は、痛みに配慮した優しい治療を心がけて診療を行っています。むし歯・歯周病治療だけでなく、矯正治療や小児歯科、インプラント治療など、幅広い診療に力を入れています。