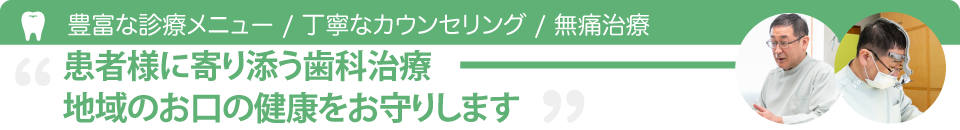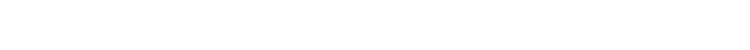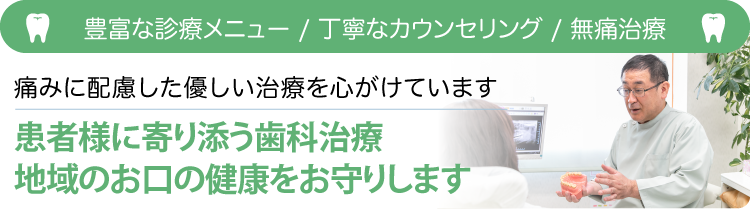こんにちは。鳥取市東町にある歯医者「山根歯科医院」です。

お子さまの前歯の隙間が気になって「これって大丈夫なの?」と不安に感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。すきっ歯は見た目の問題だけでなく、将来的な歯並びや発音、虫歯リスクにも関わるため、放置してよいのか判断が難しいポイントです。
この記事では、子どもがすきっ歯になる原因やそのままにすることで起こりうる問題、治療方法などについて解説します。お子さまの歯並びが気になる方は、ぜひ参考にしてください。
目次
すきっ歯とは?

すきっ歯とは、歯と歯の間に隙間がある状態を指し、専門的には空隙歯列(くうげきしれつ)と呼ばれます。特に前歯の間に隙間ができることが多く、見た目が気になることもありますが、必ずしも健康上の問題があるとは限りません。
子どもの場合、顎の発達や歯の生え変わりに伴ってすきっ歯が生じることがあります。
成長過程で見られるすきっ歯の多くは一時的なものです。
しかし、永久歯が生えそろっても隙間が残る場合や、隙間が広すぎる場合は、歯の本数や大きさ、顎の骨格などに原因があることも考えられます。気になる場合は、歯科医院で相談し、適切な診断を受けることが大切です。
子どものすきっ歯の主な原因

子どもがすきっ歯になる原因はさまざまです。
歯と顎の大きさのアンバランス
子どものすきっ歯は、歯の大きさに対してあごが大きすぎることで起こることがあります。特に乳歯の時期は歯が小さく、顎が先に大きく成長するため、歯と歯の間に隙間ができやすくなります。
これは、永久歯が生え揃う前に顎の骨格が先に発達する傾向があるためです。広がった顎のスペースに対して乳歯のサイズが小さいため、歯が十分に埋まらず、すきっ歯になるのです。
ただし、永久歯は乳歯よりも大きく、顎の成長に合わせて生えてきます。そのため、こうした隙間は自然に埋まっていくことが多く、心配のいらないケースも少なくありません。
遺伝的要因
親御さんにすきっ歯が見られる場合、子どもにも同様の歯並びが現れることがあります。遺伝による影響は完全には防げませんが、成長とともに変化することもあるため、経過観察が大切です。
指しゃぶりや舌癖、口呼吸などの悪習慣
長期間の指しゃぶりや舌癖は、歯並びや顎の発育に影響を及ぼす可能性があります。これらの癖があると、前歯が前方に押し出されて隙間ができることがあるのです。
また、鼻ではなく口で呼吸する口呼吸の習慣があると、口周りの筋肉が十分に発達せず、歯並びに影響を与えることがあります。
上唇小帯の異常
上唇小帯とは、上唇の内側と歯ぐきをつなぐ筋です。これが太くて長い場合、前歯の間に入り込んで隙間が生じやすくなります。
歯の本数の過不足
生まれつき歯の本数が少ない場合、歯の間に隙間が残ることがあります。
逆に通常より歯の本数が多い過剰歯が存在する場合も、歯並びが乱れ、すきっ歯になることがあります。
乳歯の早期脱落
虫歯や外傷などで乳歯が通常より早く抜けると、隣の歯が動いて隙間ができやすくなります。必要に応じてスペースを確保するための処置が行われることもあります。
子どものすきっ歯を放置するリスク

先述したように乳歯の時期に見られるすきっ歯は、一時的な現象であることが多く、必ずしも治療が必要なわけではありません。
ただし、原因によっては放置することで、次のようなリスクが生じる可能性があります。
見た目や心理的な影響
すきっ歯は見た目に影響を与えることがあり、成長過程の子どもにとっては周囲からの指摘やからかいが心理的な負担となる場合があります。これにより、自信の低下やコミュニケーションへの消極性につながることもあるため注意が必要です。
虫歯や歯周病のリスク増加
歯と歯の間に隙間があると、食べかすや汚れがたまりやすくなります。十分な歯磨きが難しくなるため、虫歯や歯周病のリスクが高まるのです。特に乳歯の時期は、永久歯への影響も考慮が必要です。
発音や食事への影響
前歯に隙間があると、サ行やタ行などの発音が不明瞭になることがあり言葉の発達やコミュニケーション能力に影響を及ぼす可能性があります。
さらに、食べ物をしっかり噛み切れなかったり、食事中に食べ物が歯の隙間に挟まりやすくなったりすることもあり、日常生活の質に影響を及ぼすことがあります。
歯並び全体への悪影響
すきっ歯を放置すると、隣の歯が隙間に移動し、歯列全体のバランスが崩れることがあります。将来的に矯正治療が必要になるケースもあるため、早期の対応が望まれます。
自宅でできる子どものすきっ歯予防とセルフケア

ご家庭でできる子どものすきっ歯予防とセルフケアの方法について解説します。
悪習慣をやめるための工夫
すきっ歯の原因になる指しゃぶりや爪を噛むなどの悪習慣をやめるためには、子どもが無意識に行う状況を減らす工夫が大切です。
例えば、手を使う遊びを増やしたり、親子でルールを決めて取り組んだりすることが効果的とされています。無理にやめさせるのではなく、子どもの気持ちに寄り添いながら少しずつ改善を目指しましょう。
また、アレルギーや鼻づまりがある場合は、耳鼻科の受診も検討し、鼻呼吸ができる環境を整えましょう。
口腔周囲筋のトレーニングを行う
口の周りの筋肉(口腔周囲筋)を鍛えることは、歯並びの発達や口元の機能を整えるうえで重要な役割を果たします。筋肉のバランスが整うことで、舌や唇の動きが安定し、歯に余計な力がかかるのを防ぐことができるのです。
具体的には、風船をふくらませる、ストローで飲み物を飲む、口をしっかり閉じてガムを噛むなどの簡単なトレーニングが役立ちます。
これらを毎日少しずつ続けることで、口腔周囲筋の発達を促し、歯並びの安定にもつながります。
正しい歯磨きと仕上げ磨き
歯と歯の間に汚れが残ると、歯ぐきの炎症や虫歯のリスクが高まります。
年齢や歯の生え方に合った歯ブラシを選び、やさしく磨くことが大切です。また、大人が仕上げ磨きをしてサポートすることで、磨き残しを防ぐことができます。デンタルフロスや歯間ブラシも活用すると良いでしょう。
よく噛む習慣をつける
食事の際にしっかり噛むことで、顎の発達を促し、歯並びの安定につながります。「一口につき30回噛む」など、具体的な目標を決めて習慣化すると効果的です。
歯科医院で行う子どものすきっ歯の治療方法

子どものすきっ歯に対して歯科医院で行われる主な治療方法について解説します。
なお、治療開始の時期は、乳歯から永久歯への生え変わりの進行状況や、顎の成長発育の状態によって異なります。
多くの場合、永久歯が生えそろう時期や自然には改善しないと判断されたタイミングで治療を検討しますが、早期に相談することで、適切な治療計画を立てることができます。
矯正治療
永久歯が生え揃ってからもすきっ歯が自然に改善しない場合、矯正治療が選択肢となります。
マウスピース矯正は装置が取り外し可能で目立ちにくいという特徴があり、軽度のすきっ歯に適応されることが多いです。
一方、ワイヤー矯正は幅広い症例に対応できる方法で、確実に歯を動かすことが期待できます。
上唇小帯の切除手術
上唇と歯ぐきをつなぐ上唇小帯が太く、前歯の間に入り込んでいてすきっ歯の原因となっていた場合、小帯の切除手術を行うことで、歯が自然に寄りやすくなります。
悪習癖の改善指導
指しゃぶりや舌で歯を押す癖、口呼吸などの悪習慣は、歯並びや噛み合わせに影響を及ぼすため、早めの改善が重要です。歯科医院では、保護者ほ方と協力しながら癖の改善をサポートします。
欠損歯・過剰歯への対応
歯の本数が少ない先天性欠如や、余分な歯がある過剰歯が原因の場合は、レントゲン検査などで正確な診断を行い、必要に応じて抜歯や矯正治療を組み合わせて対応します。
子どものすきっ歯治療後に気をつけたいポイント

すきっ歯の治療が終わったあとも、歯並びの安定と再発防止には日々のセルフケアと定期的なフォローアップが欠かせません。お子さまの健やかな口腔環境を守るために、以下の点に注意しましょう。
治療後のセルフケアと再発予防
治療後は、歯並びや口腔内の状態を良好に保つための習慣づくりが重要です。毎日の歯みがきはもちろん、歯と歯の間の汚れを落とすデンタルフロスの使用も習慣化しましょう。
また、指しゃぶりや舌で前歯を押す癖がある場合は、少しずつ改善を促すことが大切です。
食生活では、硬すぎる食品や粘着性の高いお菓子を控え、栄養バランスの取れた食事を心がけることで、歯への負担を減らし再発予防につながります。
定期検診の重要性
治療後も、歯科医院での定期検診を継続することで、歯並びや噛み合わせの変化を早期に発見できます。特に成長期のお子さまは、顎や歯の発達に伴い状態が変化しやすいため、半年から1年に1回の検診が推奨されます。
検診では、セルフケアの方法や生活習慣についての専門的なアドバイスも受けられるため、保護者の方にとっても安心です。
成長に合わせた経過観察
子どもは日々成長し、歯や顎の状態も変化していきます。
治療後も口元や歯の隙間の様子を日常的に観察し、気になる変化があれば早めに歯科医院へご相談ください。成長に合わせた柔軟な対応が、将来的な口腔トラブルの予防につながります。
まとめ

子どものすきっ歯は、乳歯の生え変わりや指しゃぶりなど、成長過程にともなう要因で起こることが多く、自然に改善されるケースも少なくありません。
しかし、原因によっては放置することで発音や噛み合わせに影響を及ぼす可能性もあるため、注意が必要です。ご家庭でのセルフケアや生活習慣の見直しは、予防や再発防止に効果的です。
とはいえ、歯並びや口元に気になる変化が見られる場合は、早めに歯科医院での相談・診断を受けることが安心につながります。
また、治療後も定期的なフォローアップを行い、成長に応じた経過観察を続けることが、健やかな口腔環境の維持に欠かせません。正しい知識と適切な対応で、お子さまの笑顔と健康な歯を守っていきましょう。
小児矯正を検討されている方は、鳥取市東町にある歯医者「山根歯科医院」にお気軽にご相談ください。
当院は、痛みに配慮した優しい治療を心がけて診療を行っています。むし歯・歯周病治療だけでなく、矯正治療や小児歯科、インプラント治療など、幅広い診療に力を入れています。