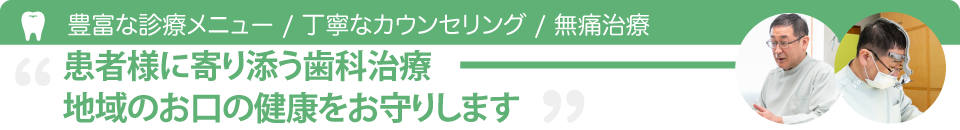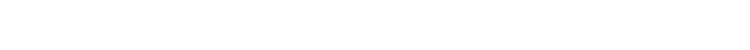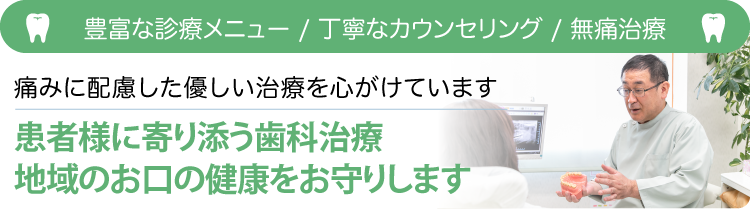こんにちは。鳥取市東町にある歯医者「山根歯科医院」です。

インプラントは「自分の歯のように噛める」「見た目が自然」といった大きなメリットがある一方で、費用が高い、治療期間が長い、外科手術が必要になるなど、見落とせないデメリットやリスクもあります。
さらに、インプラント周囲炎という感染症や、老後・全身状態の変化にともなう問題が生じることもあります。
この記事では、インプラント治療のデメリットとリスクを中心に、治療を受けないほうがよいケース、入れ歯・ブリッジとの違い、老後も見据えた注意点まで、歯科医師の立場から詳しく解説します。
メリットだけでなくデメリットも理解したうえで、ご自身に合った治療法を選ぶ際の参考にしてください。
目次
インプラント治療とは

インプラント治療は、歯を失った部分の顎の骨に人工の歯の根にあたるインプラント体を埋め込み、その上に被せ物となる人工歯を装着する治療法です。入れ歯のように取り外す必要がなく、ブリッジのように両隣の健康な歯を大きく削る必要もありません。
インプラント体には、チタンやジルコニアといった生体適合性の高い素材が使われます。チタンは骨と直接結合しやすい性質があり、顎の骨としっかり固定されることで、自分の歯に近い噛み心地を得やすくなります。
インプラント治療は、一般的に二つの段階で進みます。
最初に、歯ぐきを開いて顎の骨に穴をあけ、インプラント体を埋め込む外科手術を行います。その後、数か月かけてインプラント体と骨が結合するのを待ち、結合が安定した段階で、土台となるパーツと人工歯を取り付けて噛める状態に仕上げていきます。
天然の歯と大きく異なる点として、インプラントには歯根膜と呼ばれるクッションのような組織が存在しません。この違いが、噛んだときの力のかかり方や、後述するインプラント周囲炎などのリスクと関係してきます。
インプラント治療のメリット

この記事のテーマはデメリットですが、他の治療法と比較するためにも、代表的なメリットを整理しておきます。
自然な見た目と噛み心地に近づけやすい
インプラントの人工歯部分には、セラミックやジルコニアなどの素材が用いられることが多く、色や透明感を周囲の歯に合わせやすい特徴があります。
保険の差し歯や金属のバネが見える入れ歯と比べると、口を開けたときの見た目が自然になりやすい治療です。
また、インプラント体が顎の骨と直接結合するため、入れ歯のようなズレやガタつきが少なく、しっかり噛みやすい点も大きな利点です。硬いものを噛んだときの安定感や、食べ物が装置と歯ぐきの間に挟まる不快感が少ないことから、食事のストレス軽減につながる場合があります。
周囲の歯への負担を抑えやすい
ブリッジでは、欠損部の両隣の歯を大きく削って土台にする必要があります。入れ歯でも、金具をかける歯に負担がかかり、長期的にはぐらつきやすくなることがあります。
それに対してインプラントは、基本的に失った歯の部分だけで完結する治療です。周囲の健康な歯を削らずに済むため、残っている歯の寿命を延ばすことにつながる可能性があります。
顎の骨が痩せるのを抑えやすい
歯を失うと、その部分の骨には噛む力が伝わらなくなり、徐々に痩せていきます。入れ歯は粘膜の上に乗るだけなので、骨への刺激は限定的です。
一方、インプラントは骨の中に直接埋め込まれているため、噛む力が骨に伝わりやすく、骨のボリューム低下をある程度抑えられるとされています。顎の骨が大きく痩せると口元のシワやたるみに影響することもあるため、見た目の面でもメリットになり得ます。
インプラント治療の主なデメリット
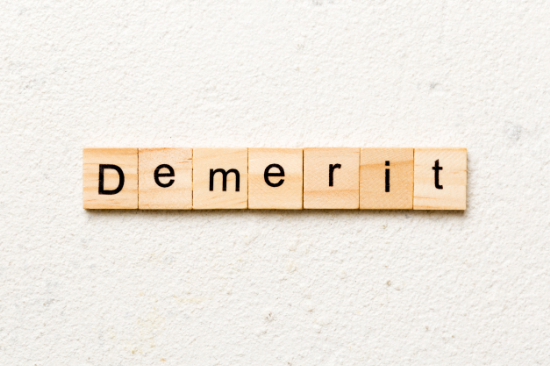
インプラントには多くの利点がある一方で、他の治療法にはない負担やリスクも存在します。ここでは代表的なデメリットを整理します。
費用が高額になりやすい
インプラント治療は、限られた特殊なケースを除き、公的医療保険の適用外となる自由診療です。そのため、保険診療の入れ歯やブリッジと比べると、1本あたりの費用が高くなります。
地域や使用するインプラントの種類、被せ物の材質によって差はありますが、1本あたりのおおよその目安は30万円から40万円前後とされています。骨造成などの追加処置が必要な場合は、さらに費用がかかることもあります。
また、インプラントは入れて終わりではなく、定期的なメンテナンスが欠かせません。3か月から6か月ごとの検診やクリーニングには、その都度の費用が必要です。治療を検討する際は、初回の手術費用だけでなく、長期的なメンテナンス費用も含めて総額をイメージしておくことが大切です。
治療期間が長くなりやすい
インプラント治療は、通常の虫歯治療や被せ物治療と比べると、治療期間が長くなる傾向があります。カウンセリングや検査、手術、経過観察、型取り、最終的な人工歯の装着までを含めると、少なくとも数回から十数回の通院が必要になることもあります。
インプラント体を埋め込んだあと、骨としっかり結合するまでには数か月の待機期間が必要です。
顎の骨の状態や全身の健康状態によって個人差はありますが、一般的には3か月から6か月程度を目安とし、骨造成を併用する場合や複数本の治療では一年近くかかることもあります。短期間で歯を入れたい方にとっては、この時間的な負担がデメリットになり得ます。
外科手術による身体的負担がある
インプラント治療では、歯ぐきを切開し、顎の骨にドリルで穴をあけてインプラント体を埋め込む外科手術が必要です。
局所麻酔や静脈内鎮静法などで痛みや不安を軽減することはできますが、まったく負担がないわけではありません。術後には腫れや痛み、内出血が数日続くこともあります。
糖尿病や心疾患、高血圧などの全身疾患がある方、抗凝固薬など特定の薬を服用している方、妊娠中の方などは、手術や術後の経過に影響が出る場合があります。
このような場合は、かかりつけ医と連携しながら慎重に判断する必要があり、状況によってはインプラント以外の治療法を選択したほうが安全なこともあります。
治療後も継続的なメンテナンスが必須になる
インプラントは虫歯にはなりませんが、歯周病に似たインプラント周囲炎を起こすことがあります。これを防ぎ、長く快適に使い続けるためには、治療が終わったあとも定期的なメンテナンスが欠かせません。
メンテナンスでは、インプラントと骨の結合状態、歯ぐきの炎症の有無、噛み合わせのバランス、被せ物やネジの緩みなどを確認し、必要に応じてクリーニングや調整を行います。
一般的には3か月から6か月に一度の通院が推奨されますが、歯周病リスクが高い方や喫煙者の方は、より短い間隔での管理が必要になる場合もあります。
定期的に通院できない生活環境の方や、セルフケアが苦手で歯磨きが十分に行えない方にとっては、この継続的なメンテナンスが負担となり、インプラントのデメリットになり得ます。
老後や再治療の際に問題が生じることがある
インプラントは適切に管理すれば長期的に使用できる治療ですが、将来、体力が落ちたり、要介護状態になったりしたときに問題が生じることがあります。寝たきりや施設入所などで通院が難しくなると、十分なメンテナンスが受けられず、インプラント周囲炎が進行してしまうおそれがあります。
また、何らかの理由でインプラントを外す必要が生じた場合、インプラントは骨と強固に結合しているため、取り除く際にも骨を削る外科処置が必要になることがあります。
高齢で全身状態が悪い場合には、この再手術自体が大きな負担となることも考えられます。老後の通院手段や、訪問診療に対応しているかどうかなども含めて、長期的な視点で検討することが重要です。
インプラント治療に伴う主なリスク

インプラント治療では、外科手術に特有のリスクと、インプラント特有の長期的なトラブルの両方を考える必要があります。ここでは代表的なものを紹介します。
上顎洞への穿孔やインプラント体の迷入
上の奥歯のインプラント治療では、上顎洞と呼ばれる空洞との距離が近いことが多く、骨の厚みが十分でない場合があります。このようなケースで適切な診査や設計が行われないと、インプラント体が上顎洞内に突き抜けたり、迷入してしまうリスクがあります。
現在は、事前にCT撮影を行い、骨の高さや厚み、上顎洞との位置関係を三次元的に把握することで、このようなトラブルの多くは予防可能とされています。
必要に応じて、サイナスリフトやソケットリフトといった骨造成術を併用し、安全な位置にインプラントを埋入していきます。
下顎の神経損傷による麻痺や痺れ
下顎の奥歯の下には、下顎管という太い神経と血管の通り道があります。インプラント体がこの神経に近すぎたり、接触してしまうと、下唇や顎、歯ぐきなどに痺れや感覚の低下が生じることがあります。
多くは時間とともに改善していきますが、まれに長期的に残ることも報告されています。
このリスクを減らすためには、やはりCTによる事前診査が重要です。神経の位置を正確に把握し、十分な安全域を確保したうえでインプラントの長さや太さ、埋入角度を決定することが求められます。
インプラントの脱落や結合不良
インプラント体が骨と十分に結合しなかった場合や、術後に感染が起きた場合には、インプラントがぐらついたり、最終的に脱落してしまうことがあります。
喫煙や糖尿病、口腔衛生状態の不良などは、インプラントの結合不良や脱落のリスクを高める要因とされています。
また、手術時の無菌操作が不十分であったり、術後の指示が守られなかった場合にも、感染リスクが高まります。術前の禁煙や全身状態のコントロール、丁寧なブラッシング指導、滅菌管理が徹底された歯科医院での手術が、リスク低減に重要です。
金属アレルギーの可能性
インプラント体に使われるチタンは、生体親和性が高く、人工関節など医療分野で広く用いられている素材です。一般的にはアレルギーを起こしにくいとされていますが、ごくまれにチタンに対するアレルギー反応が疑われるケースも報告されています。
金属アレルギーの既往がある方や心配が強い方は、事前に皮膚科などでパッチテストを受けることや、場合によってはジルコニアインプラントなど金属以外の選択肢について歯科医師と相談することが役立ちます。
インプラント周囲炎(インプラント歯周炎)
インプラント周囲炎は、インプラントの周りの歯ぐきや骨に炎症が起こる病気で、天然歯の歯周病に相当します。プラークや歯石がたまり、細菌が増えることで歯ぐきが腫れたり、出血したりしながら、進行するとインプラントを支える骨が溶けていきます。
自覚症状が乏しいまま進行することも多く、気づいたときにはかなり骨が失われている場合もあります。重度になると、インプラントの除去が必要になることもあります。
歯周病の既往がある方や喫煙者の方は、特にインプラント周囲炎のリスクが高いとされています。
このリスクを抑えるためには、治療前に歯周病治療をしっかり行い、ブラッシングや歯間ブラシ、フロスなどを用いたセルフケアを徹底することが重要です。
あわせて、3か月から6か月ごとの定期検診で、歯科衛生士による専門的なクリーニングとチェックを受けることが、長期的な安定につながります。
インプラント治療を慎重に検討すべき人

インプラントは多くの方に適用可能な治療ですが、全員に向いているわけではありません。特に次のような場合は、慎重な検討や事前の治療、生活習慣の見直しが必要になります。
強い歯ぎしりや食いしばりがある人
就寝中の歯ぎしりや、日中の強い食いしばりがあると、インプラントに過度な力が集中し、被せ物の破損やインプラント体の緩み、最悪の場合は脱落につながることがあります。
歯ぎしりはご自身では自覚しにくいため、家族からの指摘や歯のすり減り、顎の疲れなどがある場合は、事前に歯科医師に相談することが大切です。
ナイトガードと呼ばれるマウスピースを就寝時に装着することで、インプラントや残っている歯を守る対策をとることもあります。
喫煙をやめられない人
喫煙は血流を悪化させ、傷の治りを遅らせるだけでなく、インプラントと骨の結合を妨げる要因とされています。また、インプラント周囲炎のリスクも高まることが報告されています。喫煙者では、非喫煙者と比べてインプラントの失敗率が高くなるという調査結果もあります。
そのため、多くの歯科医院では、少なくとも手術前後の禁煙、可能であれば完全な禁煙を強くおすすめしています。どうしても禁煙が難しい場合は、インプラント以外の治療法を検討したほうがよいケースもあります。
歯磨きや定期メンテナンスが苦手な人
インプラントを長持ちさせるには、毎日の丁寧な歯磨きと、歯科医院での定期的なメンテナンスが欠かせません。歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロスを使って、インプラント周囲や歯と歯の間の汚れをしっかり落とす必要があります。
これまで歯科検診にほとんど通ってこなかった方や、歯磨きの習慣が不十分な方は、そのままの生活習慣でインプラントを入れると、短期間でインプラント周囲炎を起こし、除去が必要になるリスクが高まります。
インプラントを検討する前に、まずは歯周病治療やブラッシング指導を受け、セルフケアと通院の習慣を整えることが重要です。
コントロール不良の糖尿病がある人
糖尿病は、傷の治りを遅らせ、感染症のリスクを高める病気です。血糖コントロールが不十分な場合、インプラントと骨の結合がうまくいかなかったり、術後に感染を起こしやすくなったりすることが知られています。また、インプラント周囲炎のリスクも高くなります。
ただし、糖尿病があるからといって必ずインプラントができないわけではありません。内科医の管理のもとで血糖値が安定している場合には、慎重な計画のもとでインプラント治療を行うことが検討されます。まずはかかりつけ医と連携し、全身状態の把握と改善を優先することが大切です。
骨粗鬆症や顎の骨量が少ない人
骨粗鬆症は骨の密度が低下し、もろくなる病気です。顎の骨の量や質が不足していると、インプラントをしっかり固定できない場合があります。
また、骨粗鬆症の治療薬の種類によっては、顎骨壊死と呼ばれる合併症のリスクが問題になることもあります。
顎の骨の状態は、レントゲンやCTで詳しく調べることができます。骨の高さや厚みが不足している場合でも、骨造成術を併用することでインプラントが可能になるケースもありますが、その分費用や治療期間、手術回数の増加につながります。服用中の薬がある場合は、必ず事前に歯科医師に伝えましょう。
定期的な通院が難しい人や要介護が想定される人
仕事や介護、遠方への引っ越しなどで、定期的な通院が難しいと予想される場合も、インプラント治療は慎重に検討する必要があります。
特に将来的に要介護状態になる可能性が高いと考えられる場合には、訪問診療に対応しているか、インプラントのメンテナンスやトラブルに対応できる体制があるかどうかも含めて、歯科医院選びを行うことが大切です。
ブリッジ・入れ歯との比較から見たデメリット

インプラントのデメリットを正しく理解するには、他の代表的な治療法であるブリッジや入れ歯と比較して考えることが役立ちます。
ブリッジとの比較
ブリッジは、欠損部の両隣の歯を削って土台にし、その上に連結した被せ物を装着する治療です。保険適用で行える場合が多く、インプラントよりも費用を抑えやすく、治療期間も比較的短いという利点があります。
一方で、健康な歯を大きく削る必要があることや、土台となる歯に大きな負担がかかることがデメリットです。土台の歯が虫歯や歯周病で悪くなった場合には、ブリッジ全体の作り直しが必要になることもあります。
インプラントは周囲の歯を削らずに済む反面、費用と期間、外科手術の負担が大きくなる点がデメリットとなります。
入れ歯との比較
部分入れ歯や総入れ歯は、保険適用で作製できることが多く、外科手術が不要であることが大きなメリットです。高齢で全身状態に不安がある方や、外科処置に抵抗が強い方にとっては、入れ歯が第一選択となることも少なくありません。
ただし、入れ歯は取り外し式であるため、装着時の違和感や、噛む力の低下、発音への影響などが出やすい傾向があります。金属のバネが見えることを気にされる方もいます。
また、入れ歯の下の骨は徐々に痩せていくため、数年ごとに作り直しや調整が必要になることが一般的です。
インプラントは、しっかり噛めることや見た目の自然さ、骨が痩せるのを抑えやすい点で優れていますが、費用・期間・手術・メンテナンスといったデメリットを伴います。
どの治療法が適しているかは、年齢や全身状態、残っている歯の本数や状態、費用面、ライフスタイルなどによって異なります。
インプラントの寿命と長持ちさせるポイント

インプラントは「長持ちする」と言われることが多い治療ですが、実際の寿命は、使い方やお口の環境によって大きく変わります。
インプラントの一般的な寿命
インプラント体そのものは、適切に管理されていれば10年から15年以上機能することが多いとされています。20年以上問題なく使えている例も報告されていますが、これはあくまで目安であり、全ての方に当てはまるわけではありません。
一方で、入れ歯は四年から五年程度、ブリッジは7年から8年程度で作り直しや大きな修理が必要になることが多いとされており、これらと比べるとインプラントは長期的な耐久性に優れている治療といえます。
ただし、インプラントの上に装着する被せ物は、噛み合わせや食いしばりなどの影響で、数年から十数年の間に作り直しが必要になることがあります。
長持ちさせるために重要なこと
インプラントをできるだけ長く快適に使い続けるためには、日々のセルフケアと歯科医院でのプロフェッショナルケアの両方が欠かせません。
歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやフロスを使って、インプラント周囲の汚れを丁寧に落とす習慣を身につけることが重要です。
また、三か月から六か月ごとの定期検診を継続し、インプラント周囲炎の早期発見・早期治療を心がけることが、寿命を延ばすうえで大きなポイントになります。
喫煙やコントロール不良の糖尿病など、リスクを高める要因がある場合は、それらを改善していくことも重要です。
歯ぎしりや食いしばりが強い方は、就寝時のマウスピースを併用することで、インプラントや残っている歯への負担を軽減できます。
インプラント治療を受ける際の注意点

インプラント治療の安全性と成功率を高めるためには、手術前後の過ごし方や、その後の生活習慣がとても重要です。
手術前に気をつけたいこと
手術前日は、十分な睡眠をとり、体調を整えておきましょう。風邪気味や体調不良の場合は、無理に手術を受けず、事前に歯科医院へ連絡して相談することが大切です。
静脈内鎮静法などを併用して手術を受ける場合は、当日の車やバイクの運転ができません。付き添いの方に同伴してもらうか、公共交通機関やタクシーを利用するなど、あらかじめ帰宅手段を確認しておきましょう。
手術当日から数日の注意点
手術直後は、ガーゼをしっかり噛んで止血し、血の塊ができるのを妨げないようにすることが大切です。強いうがいや、ストローを使った飲み物は、血の塊が取れてしまう原因になるため、指示があるまでは控えましょう。
処方された抗生物質や痛み止めは、指示どおりに服用してください。自己判断で中断すると、感染リスクが高まることがあります。上顎の手術を受けた場合は、しばらくの間、強く鼻をかむことも避ける必要があります。
手術部位を舌や指で触ったり、強く押したりすると、傷口が開いたり、細菌が入り込む原因になります。気になっても触らないようにしましょう。
飲酒や激しい運動、長時間の入浴も、出血や腫れを助長することがあるため、歯科医師の指示があるまでは控えてください。
食事は、麻酔が完全に切れてから、やわらかいものを反対側の歯で噛むようにし、手術部位に直接強い力がかからないように注意します。
長期的な注意点とメンテナンス
インプラントを長く良好な状態で保つためには、治療後の定期的なメンテナンスが欠かせません。三か月から六か月ごとに歯科医院を受診し、インプラントの状態や噛み合わせ、歯ぐきの健康状態をチェックしてもらいましょう。
日々のセルフケアでは、歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやフロスを使って、インプラント周囲の汚れを丁寧に取り除くことが重要です。磨き残しが多い場合は、歯科衛生士からブラッシング方法の指導を受けるとよいでしょう。
帰宅後や経過観察中に、強い痛みや腫れが続く、出血が止まらない、痺れが長く続くなどの異常を感じた場合は、我慢せずに早めに歯科医院へ連絡してください。早期に対応することで、トラブルが大きくなる前に対処できる可能性が高まります。
まとめ

インプラント治療には、しっかり噛める、見た目が自然、周囲の歯を守りやすい、顎の骨が痩せるのを抑えやすいといった大きなメリットがあります。
一方で、保険適用外で費用が高額になりやすいこと、治療期間が長く外科手術の負担を伴うこと、治療後も継続的なメンテナンスが必須であることなど、見逃せないデメリットやリスクもあります。
特に、インプラント周囲炎や老後の通院困難、再治療の難しさといった点は、治療を決める前にしっかり理解しておく必要があります。毎日の丁寧な歯磨きと、歯間ブラシ・フロスを使ったケア、3か月から6か月ごとの定期検診とクリーニングを続けることで、インプラントと残っている歯の両方を守りやすくなります。
インプラントは、適切な診査・診断と、術後の管理がきちんと行われれば、十年以上にわたり機能することも期待できる治療法です。
ただし、全ての方に最適とは限りません。全身の健康状態や生活習慣、費用面、老後のことまで含めて総合的に判断することが大切です。
鳥取市東町の山根歯科医院では、インプラントだけでなく、ブリッジや入れ歯を含めた複数の選択肢の中から、その方にとって適切と思われる治療法をご提案しています。インプラントのデメリットやリスクについても、メリットと同じくらい丁寧にご説明いたします。
「自分の場合はインプラントが向いているのか知りたい」「老後のことも含めて相談したい」といったお悩みがありましたら、鳥取市東町にある歯医者「山根歯科医院」にお気軽にご相談ください。
当院は、痛みに配慮した優しい治療を心がけて診療を行っています。むし歯・歯周病治療だけでなく、矯正治療や小児歯科、インプラント治療など、幅広い診療に力を入れています。
ホームページはこちら、予約・お問い合わせも受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。公式Instagramも更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。